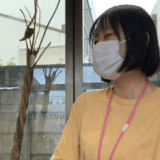在宅の現場には、薬をお届けするだけでは届かない“こころの距離”があります。薬剤師と患者さんのあいだに立ち、同じ目線で話を受けとめる――まんまる薬局の訪問サポート職「ボランチ」。
さらに栄養の視点でも伴走するのが、今回登場する鈴木涼子さんです。
2023年4月に中途入社し、ボランチとしての経験を重ねながら、最近は訪問栄養の現場にも関わる機会が増えてきました。ひとりの人として患者さんに向き合う、そのしごとの中身と想いを聞きました。
入社から2年半、最近は何をしていますか?
もちろん仕事してます(笑)
主に訪問薬剤のボランチとして、薬剤師さんと2人1組で回っています。
入社当初と比べると、訪問栄養に行かせていただく機会が増えました。
最近はボランチとしてだけでなく、栄養士としての動きも増えてきている感覚です。
新店舗の拡大に伴って、さまざまな店舗のヘルプや中業務、店舗間で移管した患者さんの情報をケアマネさんにご連絡差し上げたり、いろんなことをさせていただいています。
いま涼子ちゃんの考える「ボランチ」とは?

患者さんと薬剤師さんの橋渡しをする。
患者さんの「話したくても話せなかった。」がない場をつくる。それがボランチだと考えています。
患者さんがひとりの人として何でも話しやすい環境をつくったり、目線を揃えてあげたり、この人になら打ち明けられると信頼を獲得したりーー
そういう存在を目指して、日々どういうことをした方が理想のボランチに近づけるか考えて動いています。
今日の1日の流れをザックリ教えて!
今日はこんな感じでした。
自分が担当する患者さんをカレンダーで確認して、情報を集め始めます。
それに伴って訪問に必要な薬を集めて、薬剤師さんとダブルチェックして出発します。
最近は、午後も患者さんのお宅に訪問することが多く、道中でお昼を取ることが多いです。
午後に伺う患者さんについて薬剤師さんと確認して、午後もそのまま訪問を再開します。
薬局に帰ってきたら、処方せんの整理などを行います。
他にも残薬を数えたり仕分けたり、日付の印字がズレていたものは修正したりまき直しを行ったりします。
今日まわった1日の居宅を報告したり、今日伺った患者さんの次回訪問日の確認もして忘れずに記録しておきます。
社外でよく話す方は?

ケアマネジャーさん、看護師さん、ヘルパーさん、診療所のアシスタントさんです。
ケアマネジャーさん
外部で最もやり取りが多いのは、担当のケアマネジャーさんです。定期訪問で、いつも在宅の方が急に不在だったり、電気やエアコンが点いたままご本人が見当たらないなどの違和感があれば、まず時間をおいて再訪し、それでも留守が続く場合はすぐに連絡します。こちらからは「いつ・何回訪問したか」「何を見聞きしたか」といった事実を伝え、感じた違和感を添えて状況確認を依頼します。
ケアマネジャーさんは患者さんの日々の生活に最も近い立場にいるため、入院や一時的な外出などの情報を迅速に把握されていて、実際に連絡して入院が判明したケースもありました。
私たちが訪問の中で覚えた小さな「ん?」もその都度共有させていただくようにしています。合言葉は、「何かあったら、ケアマネさん」です。
看護師さん
薬に関する事務的な連絡事項は、薬剤師さんからの依頼を受けて看護師さんへ確実に伝達します。食事面は看護師さんが気にかけてくださることが多いため、必要に応じて一緒に課題に向き合い、調整役として連携させていただいてます。
とくに訪問栄養で関与している患者さんは嚥下に悩みを抱えることが多く、その点でも看護師さんと密に連携しています。
ヘルパーさん、診療所のアシスタントさん
お買い物やお掃除など生活まわりの状況を知りたいときは、ヘルパーさんにお話を伺います。ケアマネさんや看護師さんとはまた違う「患者さんのすぐ隣」で見えている視点で、食事の様子や日々の細かな変化も教えていただけます。細かな患者さんクセや生活リズムまで把握されている印象があります。
診療所のアシスタントさんは患者さん・ご家族・主治医の間に立ち、具体的な中身まで把握されていて凄いなと思ってます。なので、薬局と患者さんの間でうまくいかない場面では、よく相談させていただきます。そうすると、「この患者さんには〇〇のようなお話から入ると心を開いてくれましたよ!」といった、関係性を深める具体的なアドバイスをしていただけますし、患者さんご家族とのコミュニケーションが難しいときも助言やフォローをしてくださいます。
私たちの最終的な目標は、患者さんが「その人らしく」「大好きなお家」でより良く暮らせること。その実現に向けて一緒に考え、支えてくださる存在だからこそ、自然と「ありがとうございます」という言葉がみなさんに対して出てきます。
ボランチとして最近のナイスプレーはあった?

最初のころは、玄関で「薬局、来るの遅い」「そこまで来る必要ないよね」「私、薬は嫌い」と真正面から言われてしまい、正直コミュニケーションの糸口がつかめない患者さんがいらっしゃいました。無理にお薬の話へ持っていくのではなく、まずは雑談と観察を大切にして、何度も通いました。
回数を重ねるうちに、お部屋にあるものや季節の飾り、肌の艶など“その日の変化”に触れて声をかけると、少しずつ表情が和らいでいきました。ある日、ちょうどお食事の時間に伺ってしまい、思わず「おいしそうですね。お腹が空いてきちゃいました」とこぼしたら、それをきっかけに毎回お漬物を出してくださるように…。そこから会話が弾み、今では冗談も言い合える関係になっています!
結果として、お薬の話もしやすくなり、飲み方の微調整や体調の変化にも前より早く気づけるようになりました。「医療の前に、人として仲良くなること」——これが最近の私のナイスプレーです。
これから目指す姿は?
ボランチとして
患者さんの「日常」に寄り添う伴走者として、もう一歩懐に入り、同じ目線で話せる力を高めていきます。表情や肌艶、生活のちょっとした変化に気づき、それを自然な会話の入口にできるコミュニケーションの質を磨きます。
また、やまと診療所さんのPAさんのように、医師・看護師・ご家族と患者さんをつなぐ“橋渡し役”としての立ち位置も目指します。医療の方針を生活行動へ落とし込み、現場で実装されるところまで伴走できる存在でありたいです…!
そして、訪問の終わり際の数分にこそ支援の質が表れると考えています。「もうちょっと居てほしかった」と感じさせないよう、滞在中の説明や余韻のつくり方、次回につながる声かけを工夫していきます。短い時間でも安心が続くよう、患者さんの暮らしに温度を残す訪問ができるようにしていきます。
栄養士として
自分の専門性を磨き続けるのは前提。そのうえで一番大事にしたいのは、まんまるが目指す「訪問栄養の価値」を“1人の栄養士”の枠で完結させず、“1人のプレイヤー”として現場に伝播させることです。現場での小さな積み重ねで、行動で示していきます。
まんまるだからこそ尖らせられる役割があるはずとも思ってます。
医療方針を食卓の選択に落とし込む〈生活実装〉、多職種と情報を同期するための〈評価・記録の共通言語化〉、次回訪問まで続く〈買い物・調理・摂取の習慣化支援〉——この“まんまる流”をまず自分で型にして、誰が入っても同じ質で回る仕組みとして広げていく存在を目指していきます。
自分自身として

初心に返ること、周りへの感謝を忘れないこと——この二つを「考える前に体が動く」レベルまで染み込ませた人でありたいです。
なぜこの仕事を選んだのかを思い出し、関わってくれる一人ひとりに自然に「ありがとう」を手渡せる自分を目指していきます。
編集後記…
2年半前のまんまる薬局に入って間もないタイミングでインタビューさせていただいた時と今回との変化量がすさまじかったです。特に話している様子や内容から別の人と話している感覚にもなりました(笑)
それだけ壁を乗り越えてきた回数が多いと感じましたし、使う言葉にこだわってきたんだろうなという印象も受けました。
今回お話しいただいた涼子ちゃんの「これから目指す姿」にすでにこっちまでワクワクしています。
また次回のインタビューが楽しみです!